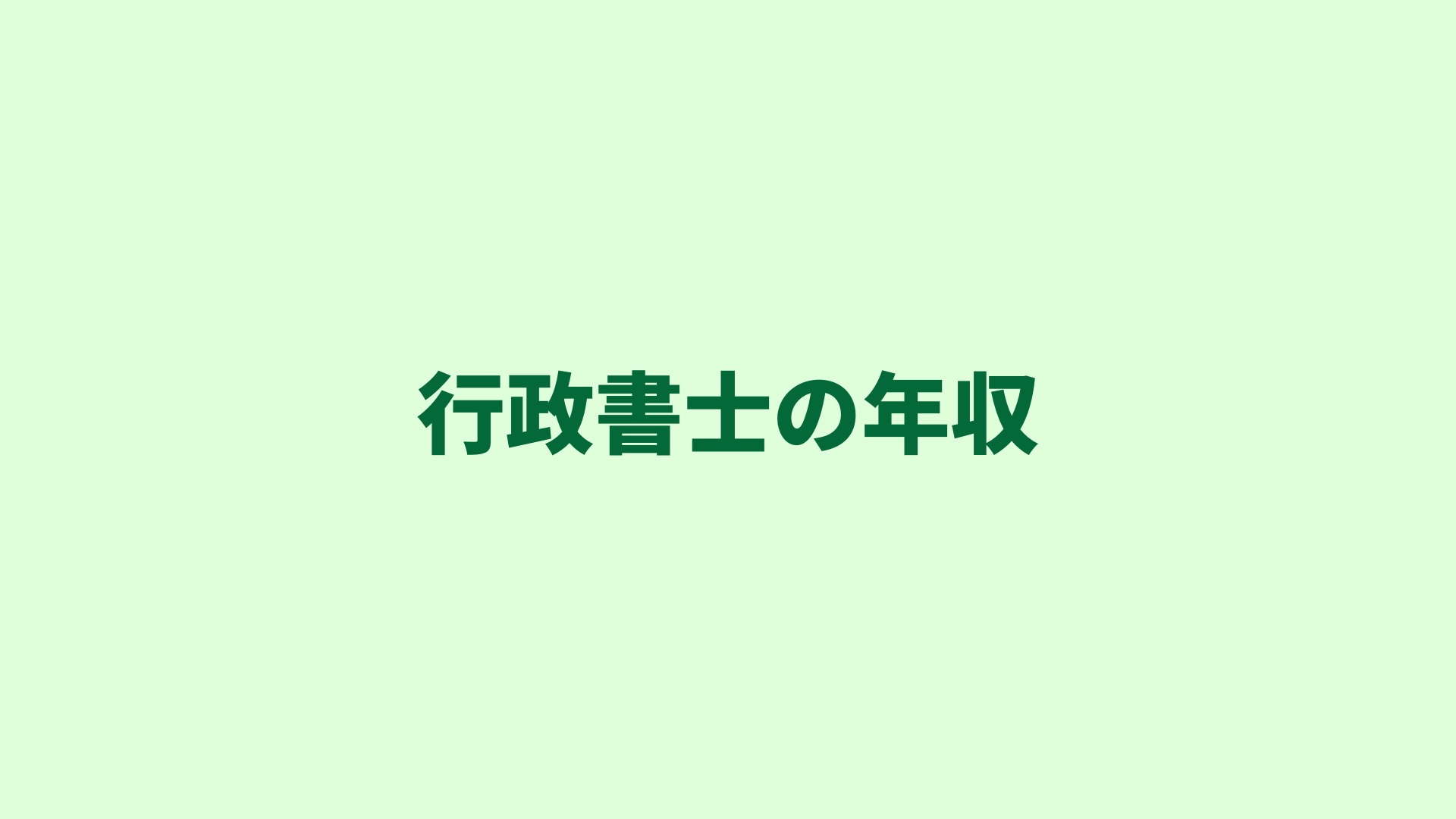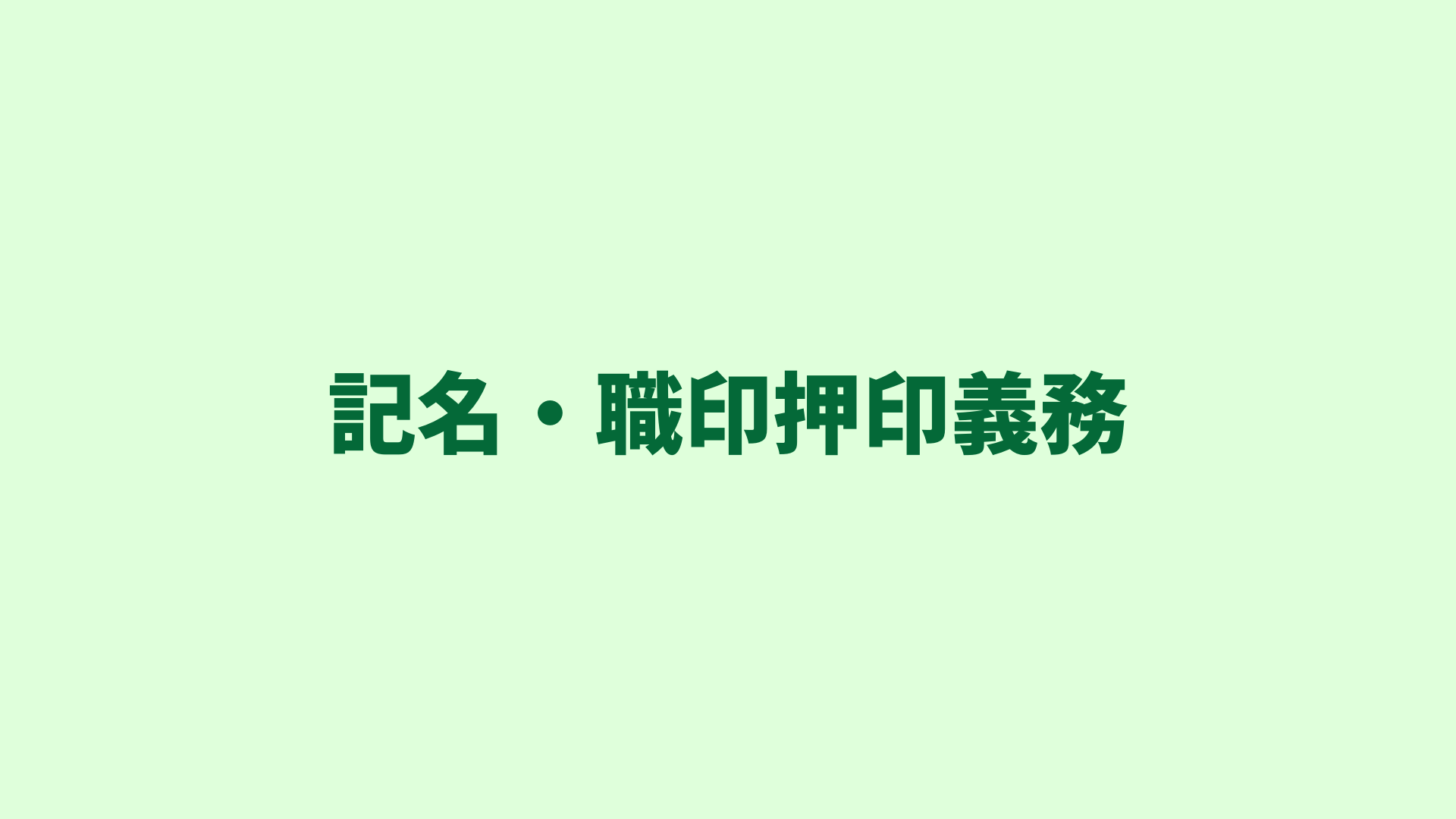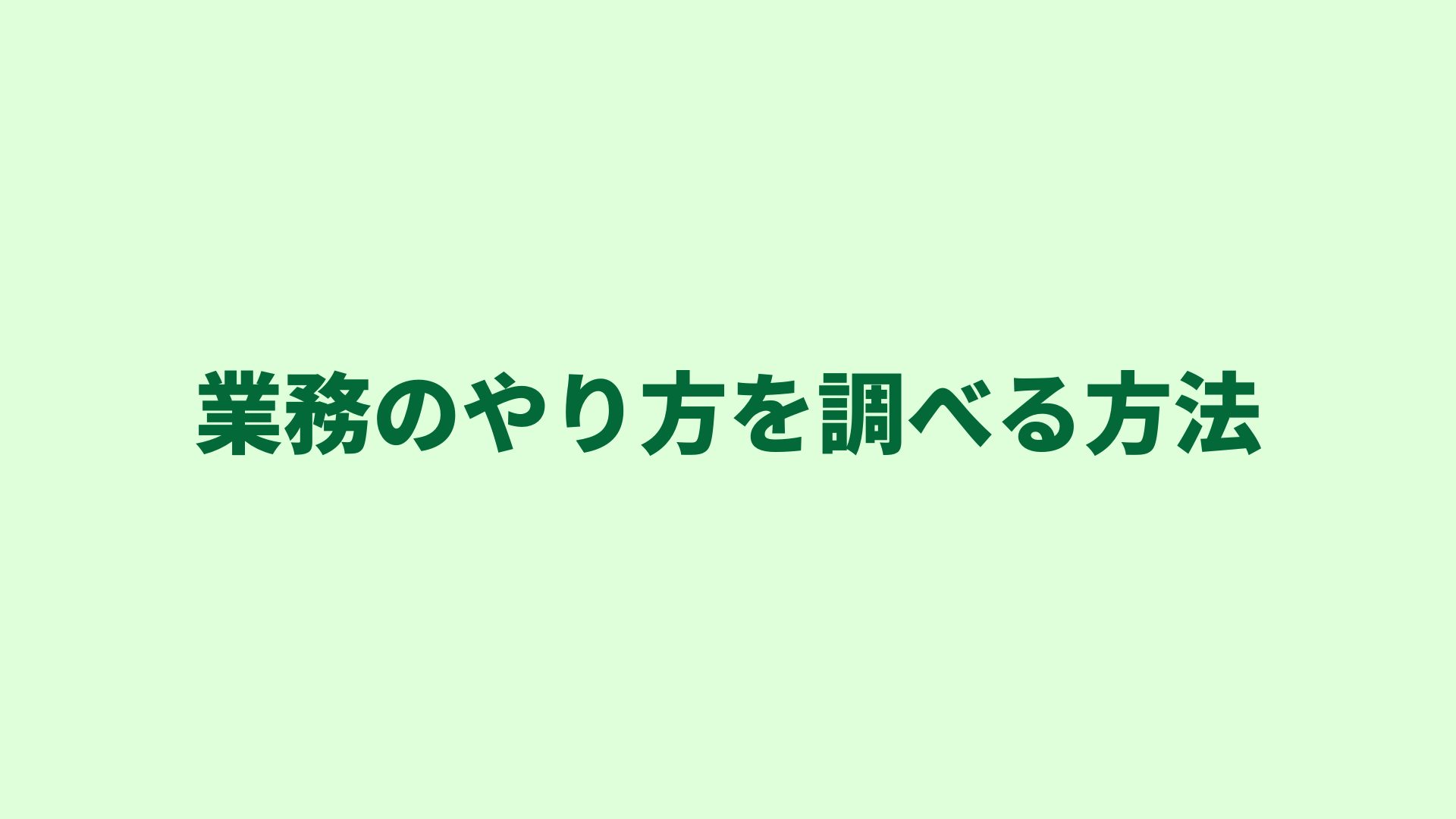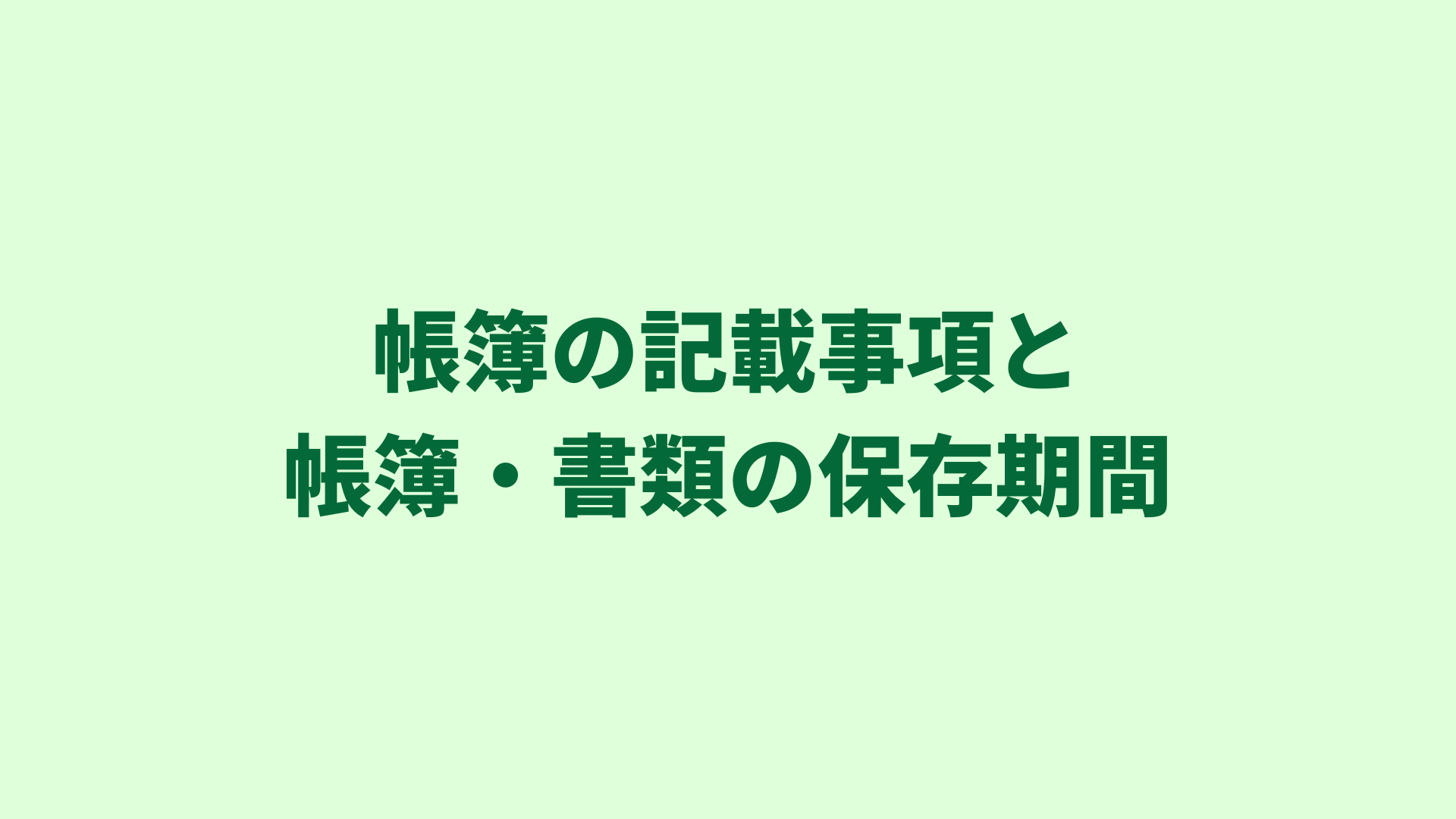行政書士補助者の仕事内容、要件、登録手続き、費用、法令などを紹介
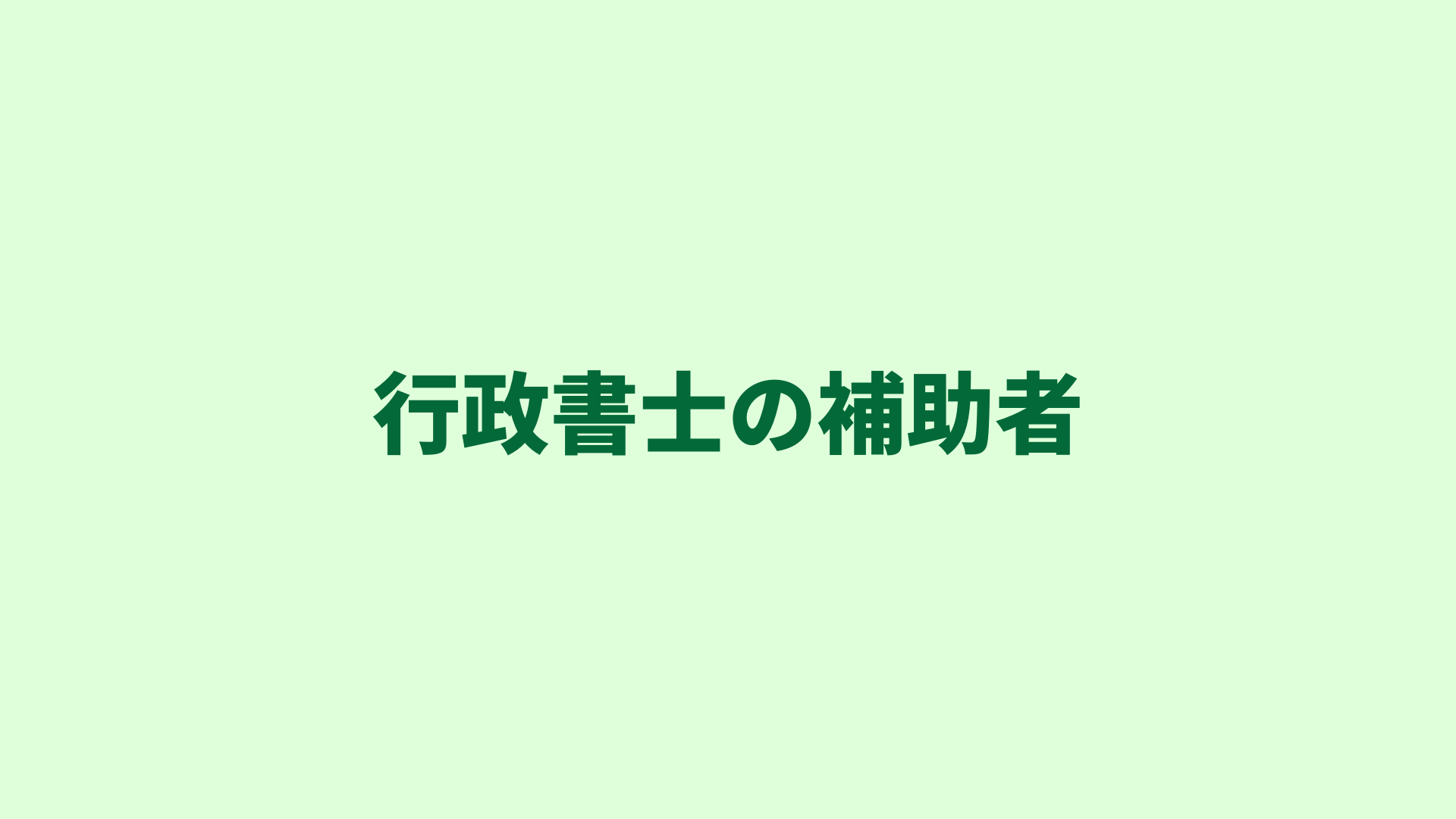
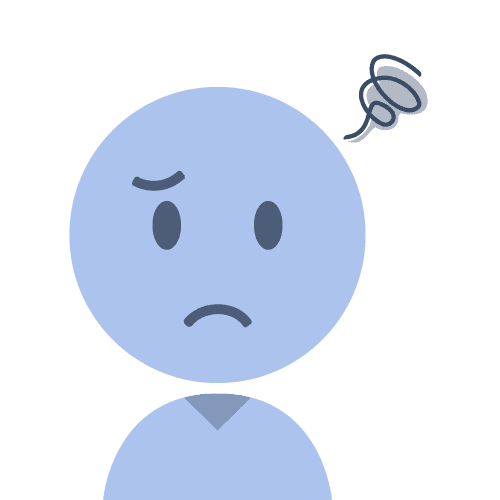
仕事が軌道に乗ったのはいいんすけど、最近やたらと忙しくて…
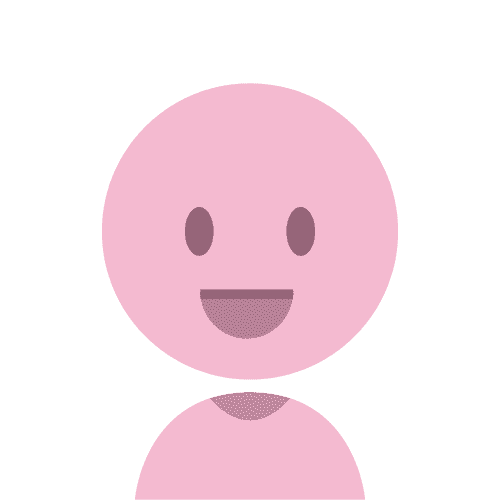
そんなに忙しいなら補助者でも雇ってみたら?
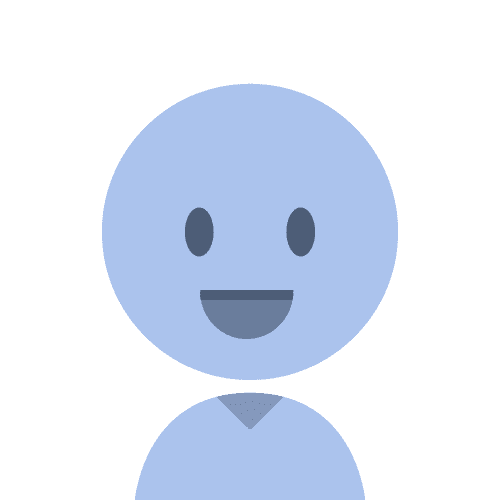
補助者か…そういえば補助者のことってあんま分かってないな…
そこで、この記事では
- 行政書士の補助者とは何をする人?
- 補助者に関して定めている法令
- 補助者の要件
- 補助者の登録手続き・費用
などについて、10年以上行政書士を続け、また、実際に補助者を雇っているわたしがご説明します。
行政書士の補助者とは?⇒行政書士業務を補助する人
それでは、まずは「行政書士の補助者」とは、何をする人なのか見てみましょう。
補助者に関するルールは、各都道府県にある行政書士会の規則によって定められています。
わたしが所属している富山県の行政書士会の規則には次のように定められています。
この規則において「補助者」とは、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第19条の3に定める「使用人その他の従業者」のうち、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第5条(第12条の3により準用される場合を含む。)に定める者であって、会員が法第1条の2及び第1条の3に規定する業務及び他法令等に基づく行政書士業務を行うにあたり、当該会員の指揮命令を受けて、当該業務に関する事務を補助する者をいう。
- 行政書士が行政書士業務を行うにあたり
- 行政書士の指揮命令を受けて
- 行政書士業務に関する事務を補助する者
行政書士の補助者とは、上記の仕事をする人ですね。
それでは、「行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務及び他法令等に基づく行政書士業務」とありますので、行政書士業務とは何か、確認しましょう。
行政書士業務とは?
行政書士業務を箇条書きで簡潔に表すと次のようになります。
- 書類の作成業務
- 書類の提出手続き代理業務
- 契約代理
- 書類の作成相談業務
- 聴聞・弁明の機会付与の手続き
- 行政庁に対する不服申立て手続き(特定行政書士のみ)
上記を見ると、ちょっと小難しい言葉も並んでおり、わかりにくい部分もあるかもしれません。
行政書士の仕事については次のページでご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
わかりやすく説明しているページはこちら▼
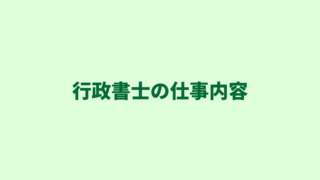
詳しく説明しているページはこちら▼
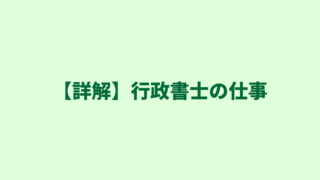
おさらいですが、補助者の仕事というのは
- 行政書士が上記の業務を行うにあたり
- 行政書士の指揮命令を受けて
- 上記業務に関する事務を補助すること
ということですね。
補助者の仕事は幅広い
上記の「事務」という言葉の定義は定められていませんが、イメージでは、相当幅広いイメージです。
手続きに使用する書類の作成はもちろん、そのほかにも
- 請求書発行したり
- 入金管理したり
- 事務所の掃除したり
- 事務所の備品管理したり
- ホームページ更新したり
なども、広い意味では事務に含まれそうです。
行政書士業務に関するありとあらゆることが仕事になりそうです。
行政書士業務ではない業務⇒補助者の仕事ではない
三度登場しますが、補助者の仕事は
- 行政書士が行政書士業務を行うにあたり
- 行政書士の指揮命令を受けて
- 行政書士業務に関する事務を補助すること
なので、行政書士が別の事業(たとえば不動産賃貸業など)も営んでいて、そちらの業務に関することをするような場合には、補助者である必要はなく、普通の従業員でもよいということになります。
それでは次は、補助者に関して定めている各種法令・条文を確認してみましょう。
補助者に関して定めている各種法令
補助者に関しては、次の法令が関係してきます(わたしの事務所がある富山県の場合)。
- 行政書士法施行規則
- 富山県行政書士会会則施行規則
- 富山県行政書士会補助者規則
ひとつずつ見ていきましょう。
行政書士法施行規則
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
ここでは、補助者に関する要件などについて、細かいことは全く書かれていませんね。
第2項に「行政書士会に届け出なければならない。」となっていることから、補助者に関する事務は、各地の行政書士会が担っていることがわかります。
- 補助者の設置・変更・廃止手続きなどは各地の行政書士会に対して行う
では、わたしが所属している富山県の行政書士会は、補助者に関してどのように定めているか、見てみましょう。
ほかの都道府県でも、多少違うところはあるかもしれませんが、そんなに大きく異なるところはないと思いますので、参考までにご覧ください。
富山県行政書士会会則施行規則
行政書士法施行規則第5条の規定により、会員が補助者を置くときは、別に定める補助者規則によるものとする。
上記のようになっており、詳しいことは「富山県行政書士会補助者規則」というもので定められています。
富山県行政書士会補助者規則のすべての条文を見るのはムリですが、一部、どんなことが書かれているのか、次で見てみましょう。
富山県行政書士会補助者規則⇒補助者の仕事内容、要件、登録手続き、費用などを定めている
こちらの規則で、補助者に関する詳しいことが定められています。
- 補助者の仕事内容
- 補助者の要件(不適格事由)
- 補助者の登録手続き・費用
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

その1.補助者の仕事内容
まずは、この記事の冒頭でご紹介した、補助者はどんなことをする人なのか?(補助者の仕事)というのがあります。
再度、見てみます。
この規則において「補助者」とは、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第19条の3に定める「使用人その他の従業者」のうち、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第5条(第12条の3により準用される場合を含む。)に定める者であって、会員が法第1条の2及び第1条の3に規定する業務及び他法令等に基づく行政書士業務を行うにあたり、当該会員の指揮命令を受けて、当該業務に関する事務を補助する者をいう。
行政書士の補助者は
- 行政書士が行政書士業務を行うにあたり
- 行政書士の指揮命令を受けて
- 行政書士業務に関する事務を補助する者
でしたね。

その2.補助者の要件(不適格事由)
ほかにも、このような定めがあります。
補助者にはなれない、不適格事由というものですね。
会員は、次の各号のいずれかに該当する者を補助者としてはならない。
一 満18歳に達していない者
二 法第2条の2第二号から第七号までのいずれかに該当する者
三 行政書士又は行政書士法人から懲戒解雇され、その日から3年を経過していない者
四 行政書士又は行政書士法人の補助者としての誠実な業務遂行が阻害されるおそれのある者
五 臨時に使用する者
第1号に「満18歳に達していない者」というのがありますので、未成年者は行政書士の補助者にはなれません。
成人した高校生はOKですね。
第2号の「法第2条の2第二号から第七号までのいずれかに該当する者」とは、いわゆる「行政書士の欠格事由」というものです。
該当する場合は行政書士になることができませんが、行政書士の補助者にもなれません。
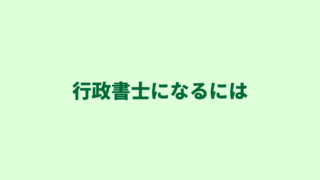

その3.補助者の登録手続き・費用
最後に、補助者を設置する場合の手続きに関してです。
会員は、補助者を置いたときは、15日以内に、次の各号に定める書類を添付して補助者設置届(様式第1号)を本会に提出しなければならない。
一 補助者となる者の履歴書(顔写真貼付)
二 会員の誓約書(補助者となる者が不適格事由に該当しない旨の誓約を含む。)(様式第2号)
三 補助者となる者の、法第19条の3に定める「秘密を守る義務」に違背しない旨の誓約書(様式第3号)
四 補助者となる者の住所を証する書面
五 補助者となる者の顔写真1枚
2 本会は、会員から前項の補助者設置届の提出があったときは、これを受理する。但し、補助者となる者が第4条に定める不適格事由に該当するおそれがあると認められる場合において、当該会員に弁明の機会を付与したにも拘わらず、当該会員がそのおそれがないことを証明できなかったときは、この限りでない。
3 会員は、補助者を置いたときは、補助者名簿を備えこれに住所氏名を記載し、補助者に提出させた次に掲げる書類と共に保存しておかなければならない。
一 履歴書(写真添付)
二 住所を証する書面
補助者を置く場合の手続きについて書かれています。
上記で出てくる「補助者設置届(様式第1号)」や「誓約書(様式第2・3号)」も規則の中に定められています。
この手続きを行うと、補助者証というものが交付されます。
本会は、会員からの補助者設置届を受理したときは、会員に補助者証(様式第4号)を交付する。
これ▼、わたしの補助者(奥さん)の補助者証です。

ちなみに、補助者の設置にもお金がかかります。
本会は、この規則に定める手続について、以下の費用を徴収する。
一 第7条第1項の届出 1,000円
二 第11条第1項の届出 1,000円
三 第12条第1項の届出 1,000円
「第7条第1項の届出」というのが、上記でご紹介した補助者を置く場合の手続きです。
ほか
- 第11条第1項の届出 ⇒ 補助者証の記載内容に変更が生じたときの変更手続き
- 第12条第1項の届出 ⇒ 補助者証の再交付手続き
です。
行政書士の会費等みたいに毎月かかるわけではないので、費用負担は重くはないですね。

まとめ
ここまで、行政書士の補助者に関してご紹介してきました。
- 行政書士が行政書士業務を行うにあたり
- 行政書士の指揮命令を受けて
- 行政書士業務に関する事務を補助する者
そして、補助者については
- 行政書士法施行規則の第5条
- 各都道府県の行政書士会の会則施行規則や補助者規則
によって、定められています。
補助者の資格や人数について特に制限はありませんので
- ある程度軌道に乗ってきたら、わたしのように家族を補助者にして節税を図ってもいいですし
- 行政書士の仕事に興味がある方は、補助者になって事前に行政書士の仕事を経験しておく
のも、よいかもしれません。